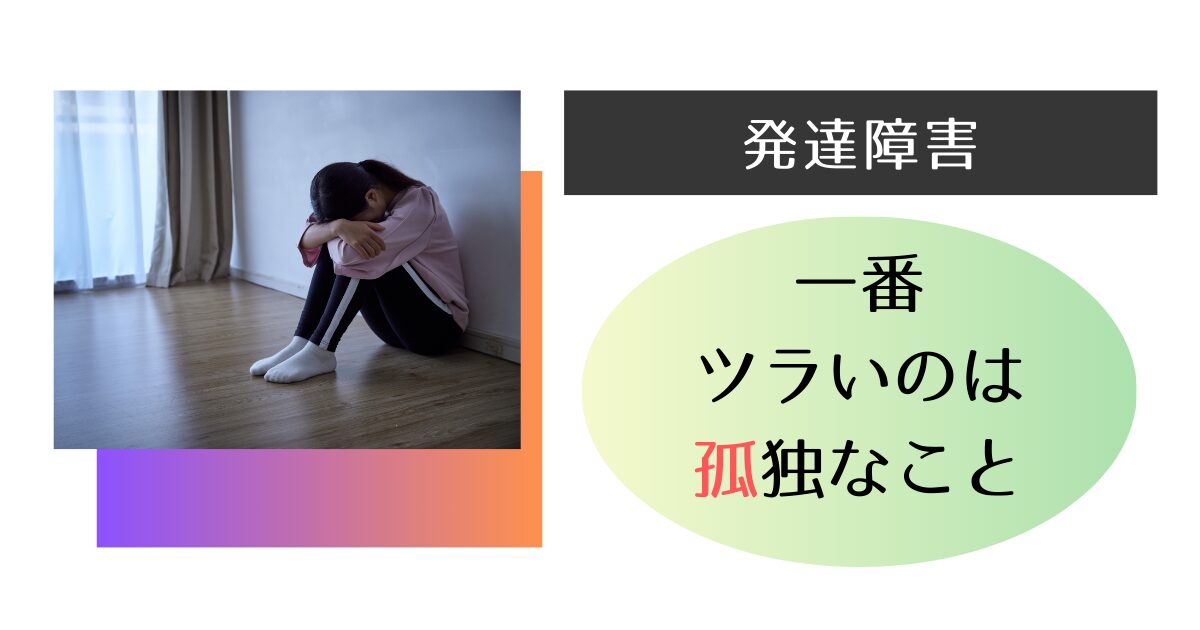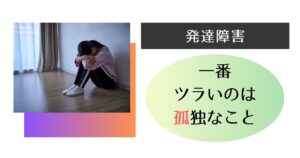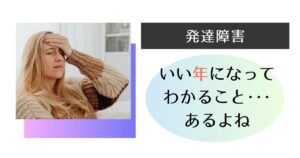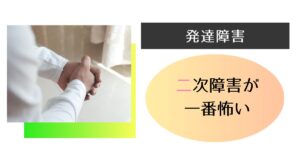みなさん こんにちは ゆーさくです。
発達障害を持つ人の多くが、「孤独」という感覚と向き合っています。
- 「理解してくれる人がいない」
- 「職場で距離を置かれる」
- 「周囲に気を遣われる」
僕自身、40歳を過ぎてADHD+ASDであることが発覚し、上司に報告した結果チームを異動しました。
仕事そのものはこなせるようになり、健康的に生きられるようにはなりましたが・・・
その一方で、今度は強い孤独感を感じるようにもなってしまいました。
この記事では僕自身の体験談も交えながら、孤独を「敵」にせず、「味方」として活かすヒントを紹介したいと思います。
-
発達障害の人が孤独を感じやすい理由
-
孤独がつらいときに起こること
-
孤独をポジティブに転換するコツ
発達障害の人が孤独を感じやすい理由
発達障害の人は、どうして孤独を感じやすいのでしょうか?
その理由を考えてみたいと思います
発達障害の主な特徴である、ASDとADHD
発達障害には、主にASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)という2つの特徴があります。
まず、ASD(自閉スペクトラム症)の特性には「人間関係の距離感をつかみにくい」という傾向があります。
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴
・雑談にどう入ればいいのか分からない
・ちょっとしたニュアンスが理解できずに会話が途切れてしまう
・本音と建て前が分からず、そのままの意味で受け取ってしまう
結果、相手からすると「冷たい人」「距離を置かれている」「空気読めない」と映ってしまうことがあります。
一方でADHD(注意欠如・多動症)の特性では、うっかりミスや抜け漏れが多い傾向があります
ADHD(注意欠如・多動症)の特徴
- 不注意によるミスをする
- 衝動的に動いてしまう
- 約束や締め切りを守れない
周囲に迷惑をかけてしまう場面が増え、本人に悪気がなくても「だらしない」「ちゃんとしていない」と思われがちです。
上記の特性を持つがゆえに、発達障害をもつ人にとって、他人と関わりながら組織の中で活躍するのは、とても難易度が高いことなのです。
うまくいかないことが増えていき、少しずつ周囲との距離が広がってしまいます。
周囲に発達障害を理解してくれる人が少ない
さらに、職場で発達障害をオープンにした場合、理解を示してくれる人ばかりとは限りません
昨今では、まだまだ発達障害はマイノリティであり、理解が進んでいるとは言えない状況です
発達障害をオープンにしたときの、周りの反応
- よそよそしくなる
- 冷たく当たってくる
- 陰で揶揄される
僕自身も色々と当事者から話を聞いていて、「仕方ない」と覚悟はしていましたが・・・
やはり、このような反応をされてしまうことが少なくありませんでした。
実際に経験すると、やはり精神的に来るものがありましたね。
「孤独を感じる」とは、単に一人でいることではありません。
たとえ、チームに所属して周りに人がいたとしても
「分かってもらえない」
「受け入れてもらえていない」
「心が通った感覚がない」
こう感じれば、それは誰が何と言おうと、その人は「孤独」なんです。
発達障害の人は、その孤独に直面しやすいのです。
 ゆーさく
ゆーさく孤独がつらいときに起こること
孤独が長く続くと、心に重たい影響が出てきます。
- 会社で雑談に加われず、「自分は仲間として受け入れてもらえていない」と感じる。
- 仕事で表面的なフォローはしてもらえるけれど、そこに「信頼関係」や「仲間意識」が薄い。
まるで存在しない人間になったようなー
周りに必要とされていない感覚に陥るんです。
こうした状態が長引くと、自己肯定感が下がり、二次障害(うつ病や適応障害など)を引き起こすリスクが高まります。
実際、発達障害当事者の方と交流すると「孤独になって、心を病んでしまった」と言っている方もいます。
診断後は「発達障害」に対しての配慮を受けられた反面、「やっぱり分かってもらえないんだな」・・・という寂しさと孤独を感じました。
孤独をポジティブに転換するという考え方
ただ、時間が経過した今だからこそ思えるようになったのですが、孤独は必ずしも悪いことばかりではありません。
むしろ、捉え方を変えれば「結構メリットあるんじゃね?」とさえ感じています。
僕はこの視点を持てるようになってから、日常がかなり楽になりました。
孤独になることのメリット
1.自分に集中できる時間を得られる
2.不要な人間関係を手放せる
3.感情が安定しやすくなる
1.自分に集中できる時間を得られる
実は、孤独=「自分のために時間を使える状態」でもあります。
周りに人がいる状態だと、思いのほか時間と精神力を使い、自分の時間が取れないものです。
孤独になることで、『誰かに振り回されることなく、仕事に向き合い、自分を磨く時間ややるべきことに使える状態』になるんです
僕の場合、孤独を感じるようになってから、これまで手をつけられなかった内省や学び、己の鍛錬に時間を割けるようになりました。
おかげで、一日の中の時間の体感がとても長く感じられるようになり、毎日の充実感が上がりました。
今まで、いかに周りの人間に合わせ、精神を削られて時間を消費していたかが、よくわかりました。
2.不要な人間関係を手放せる
孤独になると、自然と関係が絞られていきます。
それは「自分にとって大切な人だけが残る」ということです。
僕は、発達障害をカミングアウトすることで、チーム異動になり、職場でのつながりは減りました。
ほとんどの人と話さなくなり、最初こそさみしさを感じていましたが、だんだんと感じ方が変わっていきました。
- あれ? 特に無理して話す必要なかったんじゃね?
- 冷静に考えて、自分にとって必要ない人たちだったな・・・ 全然楽しくなかったし
・・・と、執着がなくなり、つながりがなくても別に困らないと思うようになりました。
その代わりに、発達障害があるとわかっても普通に接してくれる人、家族や本当に信頼できる友人との関係はより濃くなりました。
「たった数人だけど、この人たちがいてくれれば十分じゃん」
こういう考え方に変わったのです。
3.感情が安定しやすくなる
人間関係の摩擦や気疲れが減ってくると、メンタルはとたんに安定しやすくなります。
僕は、以前は職場での些細な人間関係に神経をすり減らし、一喜一憂していました
- 同僚が不機嫌な態度をまき散らすだけで「嫌われているのかもしれない」と不安になる
- 上司のちょっとした表情の変化に「ミスを責められているのでは」と過剰に反応する。
孤立することを、過剰に恐れてしまっていたんだと思います。
一日の終わりには、仕事そのものによる疲労よりも「人間関係」で疲れ果てていました。
ですが、今は「孤独でも別にいいや」と受け入れたことで、感情が振り回されにくくなりました。
孤独を和らげつつ自分を生きるための工夫
・・・とはいえ、完全に孤独になってしまうのも考え物です。
適度な「つながり」は必要です。
家族や友人と過ごす時間を大事にすること。
職場でも、深い付き合いはなくても「ちょっとした雑談ができる人」が数人いるだけで、孤独感はかなり和らぎます。
また、同じ境遇の人とつながるのも有効です。
発達障害当事者のコミュニティや交流会は、自分の悩みを分かってくれる人と出会える貴重な場です。
▼当事者会に参加した時の記事はコチラ▼


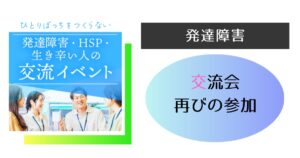
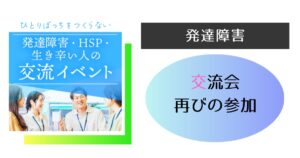
孤独を完全になくそうとする必要はありません。
「孤独7~8割、つながり2~3割」くらいのバランスであれば、孤独感を感じることなく、自分の時間や人生を大切にできるハズです。
まとめ 発達障害と孤独:職場で感じたつらさと、ポジティブに転換するコツ
まとめ
・発達障害の人が孤独を感じやすい理由
①発達障害の特性によるもの
→結果、少しずつ周囲との距離が広がってしまう
②発達障害を職場で発達障害をオープンにしても、理解を示してくれる人ばかりとは限らない
・孤独が続くと、周りに必要とされていない感覚に陥ってしまう。
→うつや適応障害などの二次障害を引き起こすリスクがある
・孤独をポジティブに変換する 孤独は必ずしも悪いことばかりではない
1.自分に集中できる
2.不要な人間関係を手放せる
3.感情が安定しやすくなる
・孤独をやわらげつつ、自分を生きるための工夫
1.家族や友人と過ごす時間を大切にする
2.職場で、ちょっとした雑談ができる人を数人作る
3.発達障害当事者のコミュニティや交流会に参加する
発達障害の人は、その特性ゆえに孤独を感じやすいものです。
職場や社会の中で「分かってもらえない」という感覚を持つことは、避けては通れないかもしれません。
しかし、孤独は必ずしも悪とは限らない
自分に集中できる
不要な人間関係を整理できる
感情が安定しやすくなる
こういう大きなメリットをもたらします。
孤独を「敵」「ダメなこと」として消そうとするのではなく、「味方」として受け入れること。
数人の信頼できる人がいれば、それで十分です。
孤独は、あなたの人生をより良く整えるチャンスになるんです。
孤独を過度に恐れず、自分の人生を取り戻しましょう!
~おわり~
▼ご意見はこちらまで▼