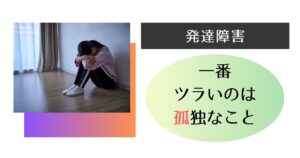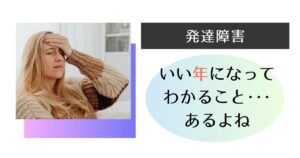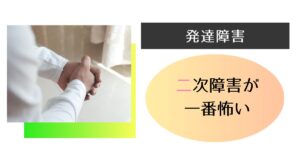みなさん こんにちは ゆーさくです
僕は、人の話や情報を耳から聞いて、理解・記憶することが昔から苦手です。
「この前言ったよね?」
「何度も説明したよね?」
「あれだけ説明して、なんで理解できないの?」
職場で何度もそう言われ、落ち込む日々―。
僕自身は真剣に話を聞いているつもりなのに、どうしてか内容が頭に残らず、覚えられないー
そんな自分を「ダメだな」「もっと集中力を鍛えないと」と責め続けていました。
でも40歳を過ぎてから、ADHDとASDの併発型であることが判明。
そこから「視覚優位」という概念を知り、世界の見え方がガラッと変わったのです。
今回は、同じように「話を聞いても頭に入ってこない」と悩んでいる方に向けて、視覚優位という特性と、その対策、そして僕自身の体験をまとめてみました。
・「視覚優位」とは?
・発達障害と「視覚優位」の関係性
・「視覚優位」の人が楽になる工夫や対策
視覚優位とは?「見る方が得意」な脳のクセ
まず、視覚優位と聴覚優位の解説をしていきます 。
視覚優位と聴覚優位の違いとは?
人には、情報を処理する時の得意な感覚があります。
代表的なのが「視覚優位」と「聴覚優位」。
- 視覚優位:文字・図・映像など「見て覚える」のが得意
- 聴覚優位:話し言葉・音・会話など「聞いて覚える」のが得意
これは、どちらが正しい、どちらが優れているというわけではありません。
ただ、ADHDやASDの人には視覚優位の傾向が強いといわれています。
発達障害と視覚優位の関係性
脳は日々、目・耳・皮膚など様々な感覚器から膨大な情報を受け取っています。
そしてその中から、「どの感覚を優先的に処理するか」は、人によって異なります。
発達障害(ADHDやASD)のある人には、「視覚優位(目で見た情報のほうが理解しやすい)」という特性を持つ人が多いとされています。
その理由のひとつは、脳の情報処理の仕方に偏りがあるためです。
たとえばADHDの人は、周囲の音や会話の中から「必要な情報だけを選んで聞く」ことが苦手です。
また、ASDの人は、抽象的な言葉よりも具体的に目で見て確認できる情報のほうが、理解しやすい傾向があります。
実際に、MRIなどの研究でも、ASDの人の脳は視覚処理に関わる領域が活発であることが報告されているそうです。
 ゆーさく
ゆーさく僕が「視覚優位」と気づいたきっかけ
僕も、発達障害持ちで、「視覚優位」の特性があります。
その特性に気づいたきっかけをお話しします。
会議で話が頭に入らず、毎回メモ地獄だった
僕は、転職を何度かしているのですが・・・
会議や普段のコミュニケーションなどが、「口頭の情報」のやりとりが多い職場は、苦手意識を感じていました。
人手不足の環境では、こういうシチュエーションによく陥ってしまうんですけどね。
特に辛かったのが、「言ったはずなのに、伝わっていない」と責められること。
- 話の中のキーワードだけが断片的に残る
- 結論や意図がよくわからない
- 「なんでわかってないの?」と責められる
そんな状況が続き、僕は自信をどんどん失っていきました。



一方で、「見て覚える」のは得意だった
ところが一方で、「見て覚える」方は比較的得意でした。
- 動画教材は理解しやすい
- マニュアルや手順書に記されていると、スッと頭に入る
- 手描きの図やイラストで説明されると一発で理解できる
このように、「理解できるとき」と「理解しづらいとき」には、実はハッキリとした違いがありました。
でも当時の僕は、その違いの理由がわからなかったんです。
僕が自分に発達障害があると知ったのは、ここ数年のこと―
そのとき初めて、自分が「視覚優位」で、「耳からの情報処理が苦手」という特性を持っているとわかったんです。
それまでは、自分にそういった特性があることも知らず、「人の話をちゃんと聞けるようにならなきゃ」と、一生懸命努力していました。
話をしっかり聞いて、必要だと思ったことはすぐにメモを取って、あとで頭の中で整理して──
でも、どれだけ頑張っても、聞いただけではうまく理解できない・・・。
苦手なものは、やっぱり苦手なままです。



「視覚優位」の人がラクになる工夫&対策
視覚による情報処理が得意で、逆に聴覚による情報処理が苦手―
これは、そういう脳の特性である以上、もう変えることはできない。
この前提に立てたとき、色々対策が見えてきました。
① 会話の内容は、必ず「見える形」にする
会話の内容は、メモ・チャット・メールなどのテキストベースにして「見える形」に残すことが大切です。
僕自身は、こんなふうに対策しています。
-
会議は議事録をとる(または録音+文字起こし)
-
口頭での指示は「メールでも送ってください」と伝える
-
複数人の会話では聞き逃しやすいので、復唱や要約を活用
テキストベースでの情報の方が、スッと頭に入るし、記録として残るので情報整理と記憶がしやすいです。
また、最近は録音+文字起こしをしてくれるガジェットもあります。
テキストベースでのやり取りが難しい場合は、そういったツールも活用しています。
▼おすすめの商品▼


② 図解やホワイトボードでの説明をお願いする
口頭のみで、かつ説明が長いと、どこが重要かわからなくなります。
図解や箇条書きで見える化されると理解が深まるので、もし可能であれば図解やホワイトボードに書きながらの説明をお願いしています。
-
スライド資料があれば、見せてもらう
- 不明点があれば、ホワイトボードに書いて説明してもらう
-
メモを書いた後、AIツールでマインドマップ化
情報を『見える化』することは、頭のパワーリソース温存になるため、なるべく視覚情報に変換してもらうように依頼したり、工夫したりしています。
③ 騒がしい場所では、情報処理を行わない
発達障害+視覚優位の僕にとって、騒音は大きな敵です。
騒音は視覚優位の人には大敵である
・周りの話し声
・電話の音
・設備や空調の音
これが単独で聞こえてくるだけなら、まだいいのですが・・・
これらの音が混じって聞こえてくると、とたんに集中できなくなり、その中で複雑な情報処理(思考+データ入力や整理)をするのが難しくなってしまいます。
- 騒がしい場所で、なるべく複雑な情報処理を行わない
- ノイズキャンセリング付きイヤホンを使う
音による情報処理が苦手のため、騒がしい環境だと集中することがどうしてもできないー
・・・で、あるならば、なるべく音が出ない環境や、状況を作り出すことが大事です。
▼おすすめの商品▼




「耳で覚えられない自分」を責めなくていい
僕は長い間、「人の話を覚えられない自分」を責めて悩み続けて続けてきました。
「なぜ、自分はこんなにも人の言っていることが理解できないのか?」と・・・
でも、それは情報処理の仕方の得意/不得意が、違っただけだったんです。
「視覚優位」という特性を知って、僕はようやく「自分に合ったやり方」を見つけることができました。
- 聞くのが苦手でも大丈夫。見ることで補えばいい
- 覚えられないのは、自分の努力不足だけではない
- 自分の特性に気づくことが、対策の第一歩
同じように悩んでいる方がいたら、少しでも参考になれば嬉しいです。
まとめ 聞いても覚えられない発達障害持ちの僕が、「視覚優位」に気づいてラクになった
まとめ
・視覚優位とは?「見る方が得意」な脳のクセ 「耳からの情報処理が苦手」
・ADHDやASDの人には視覚優位の傾向が強い
・視覚優位の人が楽になる工夫&対策
①会話の内容は、必ず「見える形」にする
②図解やホワイトボードでの説明をお願いする
③騒がしい場所では、情報処理を行わない
「視覚優位」という特性がある―
発達障害持ちであることがわかり、この概念を知ることができたとき、色々と自分に納得が出来て道が開けたような感覚がありました。
- 人の話が理解しづらいのは、「耳による情報処理」が苦手だから
- 違う方法を使えば、ちゃんと対応できる
こう思うことができました。
もし、同じような特性で苦しんでいるのなら―
「視覚を使った対策」を取り入れてみませんか?
日々のやりやすさが違ってくるはずです。
~おわり~
▼ご意見はこちらまで▼