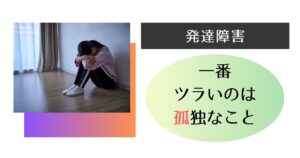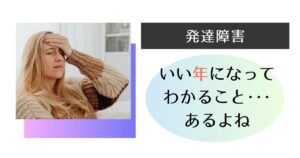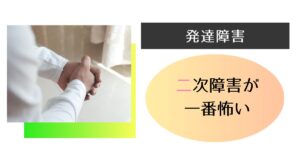みなさん こんにちは ゆーさくです。
「もしかして、うちの子にも発達障害が遺伝してるかもしれない…」
自分自身が発達障害だとわかってから、ふとそんな不安を感じる瞬間が増えました。
最近では、発達障害に関する「遺伝」の研究も進んでいて、目にする機会が増えています。
そのたびに、考えさせられることがたくさんあります。
この記事では、発達障害が遺伝する可能性について、できるだけわかりやすく解説します。
さらに、もし子どもに特性があった場合に、親としてどう向き合えばよいのか──
心の持ち方や、工夫できることについても一緒に考えていきたいと思います。
・発達障害は、遺伝するのか?
・子供に発達障害の特性が遺伝している場合の考え方
・子どもが生きやすくなるために、親ができる5つの工夫
発達障害は遺伝する?
- 「発達障害って遺伝するのか?」
- 「自分は発達障害なのだけど、自分の特性が遺伝していないか心配…」
このように、疑問や心配になる気持ち、よくわかります。
僕は、40歳を過ぎてから『ADHD(注意欠如)とASD(自閉スペクトラム症)の特性がある』と診断されました。
そして、自分の子どもに似たような特性の兆候が見えるときがあり、
 ゆーさく
ゆーさく
と、疑問に思うことが多々ありました。
そこで、色々なネット記事や解説動画を見たりしたのですが、発達障害は、遺伝的な影響がある可能性は高いそうです。
さまざまな研究でも、ADHDやASDは親子間で共通する傾向が見られることが分かっています。
たとえば──
- ADHDの子どもを持つ親の約30〜40%にも、似た傾向が見られる
- ASDについても、兄弟姉妹で同様の特性を持つ確率が一般より高い
また、以前このブログで紹介した書籍『発達障害にクスリはいらない』(三和書籍)でも、下記のような発達障害の遺伝的な要素について言及されていました。
- 発達障害と代謝のトラブルには、強い相関関係がある
- 発達障害の人は、代謝を司るメチレーション回路がうまく機能していないケースが多い
- 代謝機能がうまく働かないのは、「多型」と呼ばれる、遺伝子の一部が異常になるトラブルが関与している
引用元:『発達障害にクスリはいらない』(三和書籍)
「完全に遺伝する」と断定はすることはもちろんできないし、遺伝だけでなく、環境や相互作用も関係しているといわれていますが-
遺伝的な要因で、発達障害の特性が引き継がれる可能性は、決して低くないと僕は思っています。


子供に発達障害の特性が遺伝している場合の考え方
自分の子供に、発達障害の特性が遺伝してしまっているとしたらー
こう思うだけで、「申し訳ない」という思いがこみ上げてきます。
僕は、学生時代も、社会人になってからも、発達障害の特性に振り回されて、苦しい思いをしてきました。
・集中力が持続しない
・音に敏感で、うるさいところが苦手
・ワーキングメモリが弱く、耳から話を聞いて理解するのに時間がかかってしまう
・マルチタスクができず、混乱してしまう
そんな特性が自分の子供にも遺伝して、同じ特性に苦しめられてしまう―。
考えただけでも、いたたまれなくなることもあります。
でも、発達障害について自分なりに学び、経験を重ねる中で、考え方が少しずつ変わってきました。
確かに特性はつらいことも多い。
だけど、それは「そのまま苦しみ続けなければならない」というわけではありません。
環境を整え工夫をすれば、困りごとを最小限にして、強みを活かしながら生きていくこともできるということを、実感できるようになったんです。
そして今では、親としてやるべきことは、「遺伝してしまったことを嘆く」ことではなく、「早めに気づいて、できることをしてあげること」なんじゃないかと思っています。



子どもが生きやすくなるために、親ができる5つの工夫
では、実際に親としてどうすればよいのか?
僕自身の経験から、特に大切だと思う5つのポイントをお伝えします。
親が、発達障害(かもしれない)の子供に対して、できること・教えられること
①自分の特性をちゃんと知ること
②環境整備
③食事や生活習慣に気を配ること
④外見やふるまいにも気を遣うこと
⑤「小さな成功体験」を積むこと
①自分の特性をちゃんと知ること
発達障害は、生まれつき脳の機能に偏り(凹凸)があり、生きづらさを感じてしまう障害です
そして、そのタイプは大きく3つに分かれています
- ADHD(注意欠如多動性障害)
- ASD(自閉症スペクトラム)
- LD(学習障害)
さらにこれら3つが複雑に絡み合っていて、人によってその特性や困りごとがまちまちなのです。
だからこそ、早い段階で自分の特性をしっかり把握することが、生きやすさへの第一歩になります。
自分の特性を理解することで、苦手や困りごとに対する対処法も見えてくるからです。
自分の特性は何か? しっかり把握すること
-
集中力が続かない
-
音や光に敏感
-
コミュニケーションが独特
いわゆるチェックリストで確認するのではなく、発達障害の検査をしっかりと受けて、特性を明確にして知ることが大事です。
②環境整備
発達障害のある人は、環境や周囲の人間関係によってパフォーマンスに大きな差が出る傾向があります。
苦手なことや合わない環境は、無理に努力で何とかしようとするのではなく、環境を整備して「回避できないか?」を考えたほうがいいです。
- うるさい環境で話し声や騒音で気が散る
- 複数のことをやろうとすると混乱してしまう
- 音声による情報処理が苦手
こういった、子供に合わない環境や状況を、本人の努力のみでなんとかしようとするのは非常に大変ですし、酷というものです。
子供さん本人が無理に頑張るのではなく、環境を整備して特性が目立たないようにすることができないか?考えてみることが重要です。
③食事や生活習慣に気を配ること
上述した書籍『発達障害にクスリはいらない』では、発達障害には代謝不全が関与している可能性がたびたび示唆されています。
この代謝回路の働きを阻害し、発達障害の症状を悪化させる要因を避けることが重要と述べられています
本書では「代謝回路を阻害する4大要因」として、以下のものを挙げています。
メチレーション回路を阻害する4大要因
1.炎症(特に腸の炎症)
2.有害物質
3.栄養不足・代謝の不備
4. ストレス
これらの要因を取り除くために、食事や生活習慣に気を配り、代謝機能不全を起こしにくくすることが大切。
代謝不全にならないために、避けたほうが良いもの
- 食品添加物(着色料・保存料)
- 白砂糖、人工甘味料
- 遺伝子組み換え食品
- グルテン
- 除草剤(グリフォセート)
- 電磁波
- 有害金属
- 腸カビ(抗生物質の使い過ぎや、糖質の摂りすぎで発生)
さらに、代謝に必要不可欠な栄養素も、現代社会では不足気味になっているので、意識的に摂取するようにしましょう
- ビタミンB群(特にB6、B12、葉酸):代謝回路を活性化
- ミネラル(亜鉛・マグネシウム・鉄):脳内伝達物質の生成に関与
- 良質な油(オメガ3脂肪酸):神経の健康をサポート
- アミノ酸(タンパク質):脳内伝達物質の原料



④外見やふるまいにも気を遣うこと
少し残酷な話ですが、発達障害のある人は第一印象だけで誤解されてしまうことがあります。
- 「なんだか落ち着かない子」
- 「空気が読めない」
- 「だらしなく見える」
こういった印象を持たれないために、身だしなみやふるまい、清潔感を意識するだけで、まわりの態度が変わることがあります。
-
服装をシンプルで清潔なものにする
-
爪・髪はこまめに整える
-
最低限のあいさつやマナーは習慣化する
- 姿勢に気を配る
「見た目などの外見やふるまいの印象だけで、人からの扱いや今後の生きやすさが大きく変わる」といっても、決して言い過ぎではないと思っています。
なので、自分の子供にも「外見やふるまい」にも意識を向けて、気を配ることの大切さを伝えています



⑤「小さな成功体験」を積むこと
発達障害を持つ人は、とにかく自己肯定感が低くなりがちです
これは、人と違う特性を持っていることで、うまく物事がこなせず、「いつも失敗ばかり」「周りとうまくやっていけない」と思ってしまうことが原因です。
自己肯定感が低くなると、失敗することを恐れて物事に対してチャレンジする意欲もなくなり、結果なんの経験も積めずに、「自分では何もできない人間」になってしまうでしょう。
僕も、そうでした。
でも、人生において、「失敗しないことが最大の失敗」だと僕は思っています。
失敗を避けるがあまり、何もチャレンジせず、何の経験も教訓も得られないー
これって、長い目で見たときにかなり手痛い失敗だと思いませんか?
なので、子供には自己肯定感を持てるようにするために、「たとえ小さくてもいいから、成功体験を積んでもらう」ことを意識しています。
・ちゃんと起きれた
・宿題をすぐにやれた
・昨日まで、自分で身体が洗えなかったのに、今日はできた
こんなことでも全然OKです
・できたら大げさすぎるくらいに褒める。
・たとえ失敗したとしても、できていたところ・良かった点を伝える。
・少し前までの自分に比べ、できるようになったことが増えて前に進んでいることを、しつこいぐらいに子供に言う。
・「おまえ、すげーじゃん! やるなぁ」と言い続ける。
こうすることで、自己肯定感をはぐくみ、「自分でもできたことがある!」と思えるようになります。
その結果、きっと物事に対し「チャレンジする気持ち」を持ち続けてくれると思います。
発達障害は「扱い方にコツが必要な特性」です。
親が早く気づき、理解し、工夫することで、子どもはもっと生きやすくなります。
そしてそれは、実は「自分自身の生きづらさ」の解決にも通ずるカギかもしれません。
発達障害は遺伝する可能性はある けど、遺伝(DNA)は超えていけ!
発達障害は、残念ながら遺伝的な要素があることは否めません。
「子供に自分の特性が遺伝してしまったとしたら・・・」
時には、罪悪感に襲われてしまうことだってあるでしょう。
でも
発達障害は遺伝(DNA)による要素は確かにあるけど、そんなものに振り回されて支配され、これから先の子供の人生がすべて決まってしまうなんてー
実に気に入らないでしょう?
こちらの動画で語られていた「DNAを超える未来は創れる」というメッセージに、僕はとても勇気をもらいました。
「発達障害は遺伝する可能性は確かにある けど、遺伝(DNA)は超えていけ!」なんですよ。
環境整備や工夫次第で、発達障害の特性に振り回されることなく、元気に生きていくことを促してあげることはできるはずです。
発達障害が遺伝していたとしても、「どうやってその特性と向き合うか」を一緒に考え教えることこそが、親としての本当の役割なのだと僕は思っています。



まとめ 発達障害は遺伝するのか?
まとめ
・発達障害は「遺伝」するのか
→発達障害は、遺伝的な影響がある可能性は高い
・自分の子供に、発達障害の特性が遺伝してしまったとしたら?
→親としてやるべきことは、「遺伝してしまったことを嘆く」ことではなく、「早めに気づいて、できることをしてあげること」
・親が、発達障害(かもしれない)の子供に対して、できること・教えられること
①自分の特性をちゃんと知ること
②環境整備
③食事や生活習慣に気を配ること
④外見やふるまいにも気を遣うこと
⑤「小さな成功体験」を積むこと
発達障害は遺伝的な要素があるので、自分の子供にもその特性が引き継がれてしまう可能性はあります。
僕の子供に発達障害が引き継がれているかどうかは、まだわからないです。
「でも、もし自分の子供に発達障害が遺伝してしまったらー」
時々想像してしまうのですが、いたたまれなくなってしまいます。
でも、遺伝はすべてではありません。
DNAに影響される部分はあるとしても、それが子どものこれから先の未来を決めつけるものではないと、僕は信じたいと思います。



その子供自身が自分の特性を受け入れ、工夫して活かして生きていけるようにー
発達障害 経験者として、人生の先輩として、支えていけたらと思います
~おわり~
ご意見はこちらまで