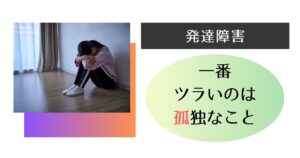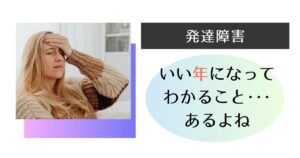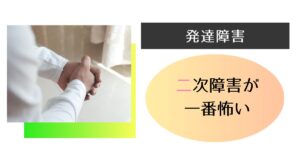こんにちは、ゆーさくです。
僕は40代になって初めて、自分に発達障害(ADHD・ASD)の特性があると知りました。
▼関連記事はこちらから▼

発達障害のある人が直面する大きな問題のひとつに、「周囲に理解者が少ない」ということがあります。
自分では精一杯頑張っているのに、上手くいかずなぜか空回りしてしまう。
「ちゃんとやってよ」「努力が足りないんじゃない?」と言われてしまい、誰にもわかってもらえず、孤独感を感じてしまう…
そんな経験をしてきた人も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな悩みを持つ人たちが集まり、自分の障害について話し合う場である「発達障害 当事者会」に参加した時のことをお話しします。
発達障害 当事者交流会に参加してみた
発達障害と孤独感
冒頭でもお話しましたが、僕は40代になって初めて、自分が発達障害(ADHD・ASD)の特性を持っていると知りました。
それまでの人生で、どこか生きづらいとは感じながらも、その原因がわからずに過ごしてきたのです。
診断を受けたことで「これまでの生きづらさの理由がわかった」と感じる一方で、同時に強い孤独感にも苛まれることになりました。
なぜなら、周囲に同じような特性を持ち理解してくれる人って、なかなかいないから。
僕は、「発達障害であることを、近しい周りの人には正直に打ち明けて」生活しています。
「大変だねぇ」「何かできることある?」…とねぎらう気持ちで接してくれる人もいます。
本当にありがたい話です
でも、発達障害ではない人(定型発達)が、発達障害の人の事を完全に理解をすることは難しい。
正直 僕に対して「どう接していいのか?」と困っている人も多いと思います。
そして、発達障害に対して偏見を持つ人や、よそよそしくなって僕から距離を置く人も少なくありませんでした。
やはり、発達障害は脳の特性による障害なので、周囲の人からは分かりにくく、理解されないのでしょう。
 ゆーさく
ゆーさく


そんな孤独感や不安を抱えるなか、ネットで「発達障害 当事者交流会」の存在を知り、参加してみることにしました。
初めての当事者交流会—参加前の不安と期待
僕が参加したのは、発達障害カウンセラー・かずきさん(発達障害カウンセラーかずき@ADHD/ASD(@kazuki_honya)さん / X)が主催する交流会
発達障害・HSP・生きづらい方の当事者交流会【ひとりぼっちを作らない】です


引用:こくちーずプロ HP
ASD、ADHDの当事者やグレーゾーンの方だけでなく、HSPや生きづらい方が集まって学びながら楽しくお喋りする交流会です。
参加する前は「うまく馴染めるだろうか?」「場違いだったらどうしよう?」と不安でしたが、それと同時に「自分と似た悩みを持つ人と出会えるかもしれない」という期待もありました。
交流会の様子
この交流会は、日曜日の午後、東京 池袋にあるビル「あうるすぽっと」の一室で行われました。
▼あうるすぽっとの場所▼
発達障害カウンセラー・かずきさんが主催するこの交流会には、さまざまな特性を持つ人たちが30人ほど集まっていました。
参加者は5~6人のグループに分かれ、ディスカッション形式で会話を進めます。
発達障害 当事者 交流会の様子
- それぞれの発達障害の特性や困りごとについて話し合う
- 20分ほどディスカッションをしたら、席替えをして新しいメンバーと話す
- 何度かグループを変えることで、異なる視点や考え方に触れることができる
- 交流会が終わった後、希望者は駅近くの居酒屋に移動し、懇親会を行う
リラックスした雰囲気の中で、より深い話をすることができました。
お話するのが苦手…という方も、各グループにスタッフの方がいてフォローしてくれるので、安心です。
※僕は次の日の仕事の都合上、懇親会には行けませんでしたが、きっと和気あいあいと楽しく過ごすことが出来る場だったのだろうと思います
発達障害 交流会で出会った人たちの悩み
実際に参加してみて思ったこと…。
それは、発達障害といっても人それぞれで、自分とは違う特性や困りごとを抱えている人がたくさんいるんだなぁということ
僕が交流会でお会いした人で、下記のようなことで苦労している人、悩まれている人がいました。
ずっと話し続けてしまう人 → 相手の反応を気にせずずーっと機関銃のように話しすぎてしまい、後から反省することが多い。
喜怒哀楽のコントロールが難しい人 → 感情が表に出すぎてしまい、人間関係に影響を与えることがある。(急に怒り出す、感極まって泣き出してしまう etc…)
コミュニケーションに悩む人 → 言いたいことをうまく伝えられず、誤解を招いてしまう。(頭の中で話がまとまらず、話が脱線気味になってしまう)
発達障害を会社に打ち明けたら、クビを言い渡されてしまった人 → 発達障害であることを伝えたら、「あなたにはもう仕事は無いです」とクビになってしまった。自分の特性を職場で開示することのリスク、打ち明けるかどうかは慎重に考える必要があると痛感した。
発達障害用の薬を服用した体験談 → 服用した際に気持ち悪くなり、結局薬をやめた。「あんな思いまでして、薬を飲み続けて働くことに、果たして意味があるのか?」と悩んでいた。
同じ発達障害というカテゴリに属していても、困りごとや悩みは人それぞれ異なるんですよね。
話を聞いていて、同じ発達障害を持っている僕から見ても、






…と思いました。
そして、皆さん自分の特性に悩み、それぞれの方法で工夫し、自分の中で折り合いをつけようとしながら生活していることにも気づきました。
発達障害者 交流会に参加してよかったと感じたこと
この交流会に参加したことで、僕が得たものは大きく3つあります。
1.「自分だけじゃない」と思えたことで、孤独感が和らいだ
僕は、発達障害の特性を持つ人が周りにいないので、とてつもない孤独感を感じていました。
交流会で同じような悩みを抱える人と出会えたことは、大きな安心感につながりました。
これまで、
「なぜ自分だけ、こんなにも生きにくいんだろう」
「どうして普通のことができないのだろう」
「こんなことを話しても、誰にも理解されない」
思い悩むことが多かったのですが、交流会で話を聞いてみると、同じような苦労を経験している人がたくさんいました。
- 「仕事でミスが多くて悩んでいる」
- 「対人関係がうまくいかない」
- 「時間管理が苦手で困っている」
こういった話を聞くと、「発達障害で困っているのって、自分だけじゃないんだ」とホッとする気持ちになり、孤独感が和らぎました。
2.発達障害と向き合うヒントを得られた
交流会では、自分と似た悩みを持つ人がどのように工夫し、考え、自分に折り合いをつけているのかを知ることができました。
例えば、
・発達障害であることを、打ち明けて仕事をしているか? その後、どうなったか?
・発達障害であるとわかった時、どうやって自分自身に納得したのか?
・発達障害の薬って、何を使っている? 副作用とかどう?
他の人がどのように工夫しているのか? 自分の発達障害をどのように捉えているか?
生の体験談や考えを知ることで、自分にも取り入れられる考えや、気づきを得られたのも大きかったです。
3.「違いを受け入れる」大切さを思い出した
交流会には、さまざまな特性を持つ人が参加していました。
同じADHDでも、衝動性が強い人、忘れ物が多い人、過集中になりやすい人など、それぞれ違った特徴を持っています。
ASDの人でも、こだわりの強さが目立つ人もいれば、対人関係の苦手さを感じやすい人もいる。
さらに、ADHDとASDの両方の特性を持つ人もいて、一口に「発達障害」と言っても、まったく同じ人はいないのだと改めて実感しました。
話をすると、最初「この人の特性とは、僕はちょっと違うな」「ちょっと理解できない感覚…」と感じることもありました
でも、話を聞いていくうちに「違いはあるけど、同じ発達障害という特性を持つ、戦友なんだよな」という、違いを受け入れる気持ちになってきました。
人は、自分とは違い理解できないものに関しては、嫌悪感や拒否反応を持ってしまうものです。
これからも、自分とは違う考えや特性に触れたとき、「分からないから排除する」のではなく、「自分とは違うけど、それでも全然OK!」という気持ちを忘れずにいたいと思いました。
まとめ—発達障害の人こそ、交流会に参加してみてください
まとめ
発達障害を抱えると、時に強い孤独感に苛まれることになる
→周囲に同じような特性を持ち理解してくれる人って、なかなかいないから。
発達障害カウンセラー・かずきさんが主催する当事者交流会に参加した
- 同じ発達障害の悩みを抱える人と話すことが出来、孤独感が和らいだ
- 発達障害と向き合うヒントが得られた
- 自分とタイプの違う発達障害の方と話をして、「違いを受け入れる」大切さを思い出した
発達障害を持っていると、社会のなかで孤独を感じてしまうことがあります。
しかし、同じ発達障害を悩みを共有できる場に身を置くことで、「一人じゃない」と思えるようになります。
もし発達障害による孤独感に悩んでいるなら、当事者交流会に参加してみるのも一つの方法です。
ネットだけでは得られない、生の声や共感が、あなたの心を軽くしてくれるかもしれませんよ。
発達障害カウンセラー・かずきさんが主催する当事者交流会 発達障害・HSP・生きづらい方の当事者交流会【ひとりぼっちを作らない】の申し込みはこちらから
※東京と大阪で、定期で開催されています。


~おわり~
ご意見、ご感想はこちらまで
↓↓