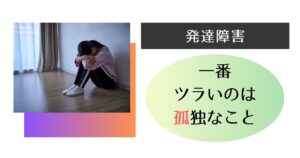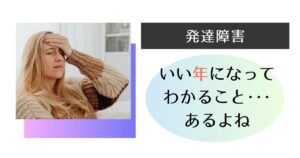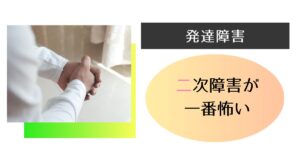近年、「ニューロダイバーシティ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
発達障害やグレーゾーンと呼ばれる人が、社会で生きやすくなるための考え方として注目されています。
あらためまして、みなさん こんにちは ゆーさくです
僕自身も40歳を過ぎてからADHDとASDの併発タイプであることが発覚し、この考え方に救われた一人です。
発達障害を抱えて働く中で感じた困難、そして環境や周囲の理解によって働きやすさが大きく変わる経験をしてきました。
この記事では、ニューロダイバーシティの意味・注目される理由・発達障害グレーゾーンのリアルについて解説していきます。
・ニューロダイバーシティって、何?
・ニューロダイバーシティが注目される理由
・ニューロダイバーシティと発達障害当事者のリアル
ニューロダイバーシティって、何?
ニューロダイバーシティとは?
ニューロダイバーシティとは、「神経の多様性を尊重しよう」という考え方です。
発達障害には学習障害、ADHD、自閉スペクトラム症など、色々な特性がありますが・・・。
ニューロダイバーシティは、それらを「障害」ではなく「脳の違い」として捉えます。
従来は
- 「できない部分は直さなければならない」
- 「できない人=ダメな人」
こう考えられてきましたが、ニューロダイバーシティの考えでは「その人が持つ特性を理解し、強みを活かす」ことが重視されます。
欧米の企業では、すでにダイバーシティ推進の一環として取り入れられています。
少しずつではありますが、日本でも大手企業や外資系を中心に、広まりつつあるのです。
僕の今務めている会社も、外資系の要素があり、この考え方を大切にしているため、当事者として非常にありがたく感じていますね。
 ゆーさく
ゆーさくニューロダイバーシティがもたらすメリット
ニューロダイバーシティの考え方は、発達障害 当事者と企業や社会 双方見メリットがあります
当事者にとってのメリット
-
生きづらさが軽減される
-
発達障害の特性を「武器」として活かせる
-
ADHDの発想力や行動力
-
ASDの集中力や正確性
-
企業や社会にとってのメリット
-
多様な発想がイノベーションにつながる
-
離職率が下がり、人材定着につながる
-
職場の心理的安全性が高まる
つまり、当事者だけでなく企業や社会全体にとって「Win-Win」の関係を作れるのが、ニューロダイバーシティの大きな魅力です。
なぜ今、ニューロダイバーシティが注目されているのか?
昨今、ニューロダイバーシティが注目されてきている背景には、以下の理由があります。
ニューロダイバーシティが注目されている背景
①発達障害の診断や検査が一般化し、認知度が上がってきた
②大人になってから発覚するケースが増えている
③働き方改革や、多様性重視の社会的流れがある
④人材不足が深刻化し、個々の強みを活かす必要性が高まっている
① 発達障害の診断や検査が一般化し、認知度が上がってきた
かつては発達障害という概念は、世の中であまり知られていませんでした。
こう片づけられてきたことも、現在では発達障害やその特性として、徐々に理解されるようになりました。
WAIS-Ⅳなどの発達障害の検査の精度も高まり、医師や専門機関で相談できる環境が整ってきています。
その結果、「発達障害は特別な一部の人だけの話ではない」と、多くの人に認知されるようになってきました。
② 大人になってから発覚するケースが増えている
子ども時代には診断に至らなかった人が、大人になって社会に出てから発達障害が発覚するケースがあります
- 「仕事がうまくこなせない」
- 「人間関係でつまずく」
- 「体調を崩し気味になる」
こういった困りごとをきっかけに、体調を崩して心療内科を受診し、初めて発達障害の診断を受ける・・・というケースが多いのです。
僕自身も、40歳を過ぎてからADHD+ASDの診断を受けました。
キッカケは、仕事がうまくこなせず体調を崩すようになり、心療内科に通院していたときに、偶然発覚しました。
関連記事はこちから
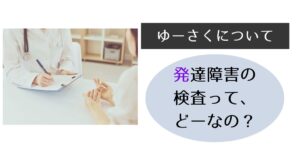
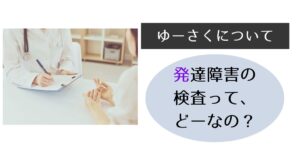
こうした「大人の発達障害」が注目されるようになったことで、ニューロダイバーシティの必要性も強調されるようになったのです。
③ 働き方改革や、多様性重視の社会的流れがある
テレワークやフレックスタイム制度の導入など、ここ数年で働き方が大きく変わりました。
同時に、個々の様々な違いを尊重する、ダイバーシティ推進が社会全体で進むことになったのです。
個々の様々な違い
- ジェンダー
- 国籍
- 宗教
- ライフスタイル etc・・・
その延長線上で、「個々の神経や認知の多様性」も受け入れるべき・・・
こういう動きが高まってきています。
④ 人材不足が深刻化し、個々の強みを活かす必要性が高まっている
少子高齢化により労働力人口が減少する中で、企業は「誰も排除せず、多様な人材を活かす」ことを余儀なくされています。
近年、未曽有の人で不足で、働き手が少なくなってきているので、どの企業も人材を選り好みをしている状況ではないのです。
発達障害やグレーゾーンの人は、不得意な面もある一方で、記憶力や集中力、独創的な発想などの強みを持っていることが多いです。
ニューロダイバーシティは、そうした人材を埋もれさせず、戦力として活かすための重要な考え方になっています。



このように、世の中を取り巻くさまざまな要素が重なったことで、ニューロダイバーシティは単なる理想論ではなくなってきています。
「今まさに必要とされる現実的な考え方」として、注目されているのです。
ニューロダイバーシティと発達障害当事者のリアル
いわゆる「発達障害 グレーゾーン」と呼ばれる人たちは、表面上は普通の人間に見えるため、周囲に理解されにくいのが現実です。
-
仕事の抜け漏れが多く「怠けている」と思われる
- 周囲の音や光が気になり、パフォーマンスが落ちてしまう
-
周囲のペースに合わせられず「協調性がない」と誤解される
-
強いこだわりを持っていると「わがまま」と受け止められる
本当は能力や強みがあるにも関わらず―
環境が合わないだけで仕事をうまくこなしたり、人間関係を構築したりすることが難しくなり、周りから評価されにくいのです。
そして、だんだんと周りから距離を置かれ、孤立してしまう可能性があります。
僕も、発達障害の特性ゆえに、うまくパフォーマンスが上がらず、苦しい思いをした経験があります。
僕自身では、かなり一生懸命やっていたつもりですが・・・。
発達障害の特性が色濃くでてしまい、今思えば頑張りが回っていた気がします。
だんだんと周りからも嘲笑され、つねに孤独感にさいなまれることになりました。
もしあの時、発達障害に関しての正しい理解が、周囲の人にも広まっていれば・・・
僕の人生は、もう少し違ったものになっていたかもしれません。



なので、当事者の僕は、声高らかにして言いたいのです。
ニューロダイバーシティの考え方が、もっともっと広まって浸透していってほしいと。
ニューロダイバーシティは、まだまだ日本では広まり始めたばかりです。
しかし、この考えが浸透すれば、発達障害のある人だけでなく、誰にとっても働きやすい社会につながるハズです。
-
特性を持った人を排除せず、力を発揮できる場所を作る
-
健常者・当事者の両方にとってストレスが減る
-
「違いを受け入れる」ことが当たり前になる
僕自身も、今後の社会が少しずつ変わっていくことに、期待したいです。
まとめ ニューロダイバーシティとは?発達障害と働き方の新しい関係
まとめ
・ニューロダイバーシティって?
→「神経の多様性を尊重しよう」という考え方
→当事者だけでなく、企業や社会全体にとって「Win-Win」の関係を作れるメリットがある
・ニューロダイバーシティが注目されてきている背景
①発達障害の診断や検査が一般化し、認知度が上がってきた
②大人になってから発覚するケースが増えている
③働き方改革や、多様性重視の社会的流れがある
④人材不足が深刻化し、個々の強みを活かす必要性が高まっている
・ニューロダイバーシティと発達障害当事者のリアル
→「発達障害 グレーゾーン」と呼ばれる人たちは、表面上は普通の人間に見えるため、周囲に理解されにくい
→ニューロダイバーシティの考えが浸透すれば、発達障害のある人だけでなく、誰にとっても働きやすい社会につながる
ニューロダイバーシティは、障害を「直す」「無かったこと」にするのではなく、「違いを尊重する」ことです。
発達障害やグレーゾーンの人も、環境や周囲の理解&サポートさえあれば、十分に能力を発揮できる可能性を秘めています。
このニューロダイバーシティの考えがもっと浸透し、発達障害をもつ人が生きやすい世の中になることを願ってやみません。
~おわり~
▼ご意見はこちらまで▼