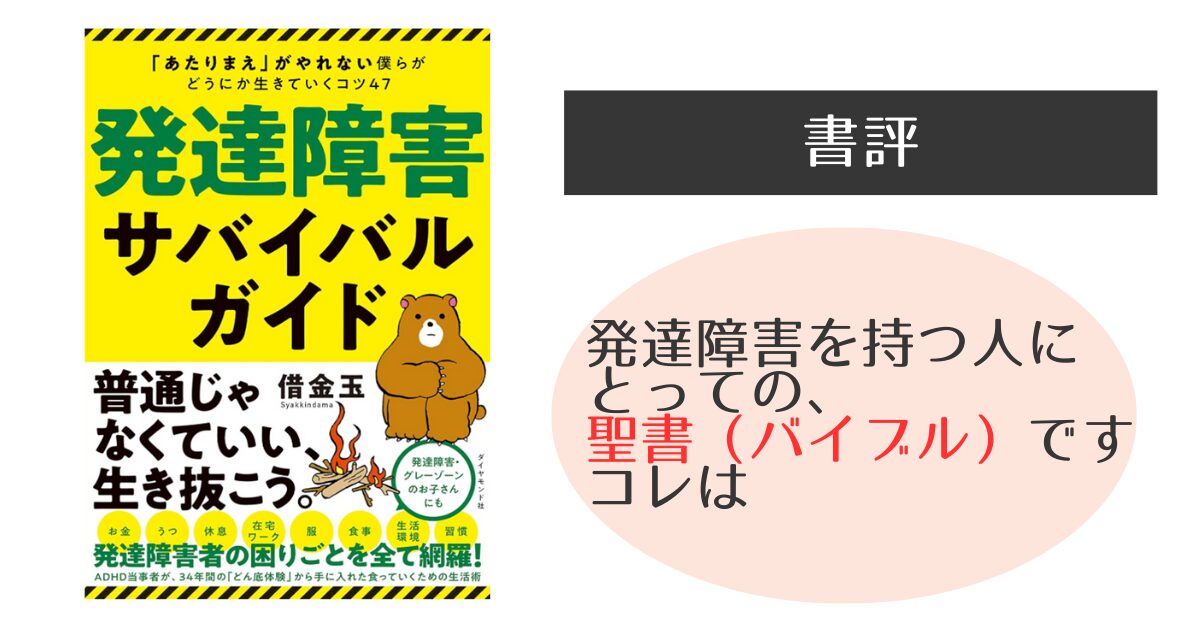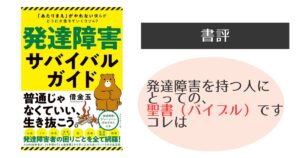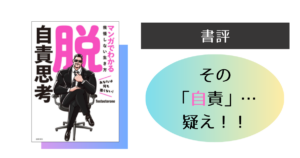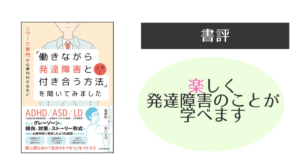みなさん こんにちは
ゆーさくです。
僕は、発達障害があることが40歳を過ぎてから発覚…
中年になってから発達障害持ちの人生を歩み始めたという、ちょっと異色の経歴を持っています
詳しくは、こちらの記事をご覧ください↓↓

40歳過ぎてから発達障害があることが分かり、僕はまぁまぁショックで絶望感を味わったのですが…
発達障害を持っている人で、上手く工夫をしながら生きている人っていないのかな?
もしいらっしゃるなら、是非参考にさせてもらいたい。
こう思い、発達障害の方向けの本を色々と読み漁ることにしたのです。
その中で『借金玉さん』(借金玉(@syakkin_dama)さん / X)が書いた本が、非常に勉強になりました。
「発達障害サバイバルガイド
出版社ダイヤモンド社

この記事では、この発達障害サバイバルガイドを読んだ感想と、個人的に勉強になり印象に残ったことを抜粋して紹介したいと思います。
「発達障害サバイバルガイド」を読んだ感想
まず、この「発達障害サバイバルガイドを読んだ感想ですが…
この本、発達障害を持っているすべての人は、一度読んでおいた方が良いと思いました。
まさしく、発達障害者にとっての聖書(バイブル)!
発達障害を持っている方が良く陥る困りごとに対し、すぐに実践できるような対策が分かりやすく説明してあり、かなり気楽な感じで楽しみながら読める内容になっています
仕事、掃除、料理、お金、人間関係… それぞれのシチュエーションで発達障害者が遭遇するであろう「困りごとあるある」が、幅広く網羅されています。
それゆえ、多くの発達障害者に刺さると思います。
また、時折出てくる、著者を模したと思われるクマちゃんのイラストがとてもかわいくて、なんかクセになるんですよね。
引用:『発達障害サバイバルガイド』
また、自身が発達障害を持っていない健常者の方でも、周囲や家族に発達障害を持つ人間がいる…というパターンもあると思います
周囲の発達障害を持つ人をサポートをする立場の人にとっても、この本は大いに役に立つと感じています。
発達障害サバイバルガイド 参考になった3つの箇所
それでは、僕がこの本を読んで個人的にタメになった箇所、参考にしたいと思えた箇所を、3つほど抜粋して紹介したいと思います(※)
(※)発達障害といっても、色々な特性があり、人によって困りごとは千差万別です。
あくまでも僕自身が持っている特性や困りごとに対して、参考になったという内容なので、ご了承いただければ幸いです。
机とイスはあなたの家の知的生産拠点
現代社会において、何かを作り出すための根源的なツールとは何か?
それは、知識だと著者は説いています。
この社会で自立して生きていくためには、「知識を手に入れ、まとめ、行動する」必要があります。
必要な知識を手に入れ、それを武器に変えて自分の切り開いていかないといけません。
これは、発達障害を持っている人間にとっては特に重要で、強く意識しておきたいところです。
知識を得るためには自宅に「知的生産拠点」を持つことが大事。
すなわち、「学習しやすい机と、座り心地のよいイス」を用意するということです
勉強や仕事をするなら、リビングの机や、コタツ机でも事足りると思う方がいらっしゃいますが…
長時間座ることや作業効率を考慮すると、あまりお勧めできません。
長時間座っても疲れず、効率化された学習しやすい机とイスをきちんと用意すべきなのです。
ライフハック:効率化された学習しやすい机とイスを用意して、「知的生産拠点」をつくる
【ポイント】
・必要なものに、一手で手が届くこと
・作業スペースを広くとる
・身体の負荷を小さくする
・チェックが大切なものが、常に視界に入るようにする
この中で、作業スペースを広くとるというのは、非常に大事であると僕自身も実感しています。
著者の借金玉さんと同様、僕はワーキングメモリが極端に弱く、短記憶で物事を覚えておくことが出来ません。
何をどこに置いたかすぐ分からなくなるし、PC作業と紙ベースの書く作業をうまく切り替えてマルチにこなすことができません。
なので、広い作業スペースを用意するなどの対策を入れることで、この欠点が目立たなくなるんですよね。
僕ら発達障害持ちは、パフォーマンスが作業環境に大きく左右されます。
環境整備は、徹底して行うべしと声高らかに言いたい
・机は人生をつくり出すもの。工夫しすぎて損はない
引用:発達障害サバイバルガイド
発達障害的型付けの最重要アイテム「本質ボックス」
発達障害を持つ方は、片づけが苦手という特性を持つ人が多いように思います。
ご多分に漏れず、僕もそうです。
いつの間にか部屋が散らかり、モノは使いっぱなしで放置…
「あれ、どこいったっけ?」となる頻度が、かなり高い。
頑張って片付けようとはするんですけどねぇ…
かなり気合を入れて波に乗らないと、お片付けができません。 奥さんに怒られてばっかりです。
この本には、そんな発達障害特有の「お片付けができない」という困りごとに対し、「本質ボックス」を作ることを推奨しています
これは「部屋の中で定位置が決まってないモノは、全部ひとつの箱にぶち込んで管理する」…というやり方です。
ライフハック:お片付けができない人に推奨 「本質ボックス」
定位置が決まっていないモノは、本質ボックスにぶち込んで管理する
・箱は、中身が見えるスケルトンか、網目状のもの。フタはつけない
・本質ボックスは、最大3つまで。それ以上増やさない
・本質ボックスからモノがあふれたら、捨てる
僕は、このやり方に少しアレンジを加えて運用しています
・箱は、大きめの段ボールを3つ用意する(※)
・散らかっているものを、下記の3つに分類してぶち込む
①メルカリで売れそうなもの、定位置や戻す場所が安易に想像できるもの
②あんまり要らないかも…と思えるもの
③その他(現段階で、取っておくのかどうか? 判別が難しいもの)
・気が向いたらその中のモノのうち4~5個だけ確認、片づけたり処分したりする
このやり方を導入してから、「アレ…どこ行った?」とモノを探す時間が極端に減りました。
まとめてその中にぶち込んであるので、この「3つの箱の中のどっかにはあるだろ」という謎の安心感が、僕のストレスを軽減してくれたように思います。
片付けが苦手で、探し物を良くしている人は、この本質ボックスにとりあえずぶち込む…をするだけでも、ストレスは軽減すると思いますよ
※ちなみに、最初僕は「中身が見えるスケルトンの箱」を用意しようとしたのですが…
「大きめのボックスを、わざわざ買うと高い」という理由で、奥さんに止められました。
スーパーでタダでもらえる、段ボールを代用して使っています。
インテリア的にはイマイチですが、そこを気にしなければお金がかからずGoodです
野菜を入れていた段ボール箱だと、土や葉っぱの残骸などがついていることが有るので、スナック菓子などを詰めていたものがおススメですよ!
すっぽかしをゼロにする「究極カレンダー」
家や勤務先で、壁掛け(もしくは卓上のカレンダー)に予定を書き込んでいる人は多いと思います。
机から今日の予定や、月単位の予定を俯瞰して見えるので、とても便利です。
ですが、著者は、このカレンダーに書き込むスケジュール管理の方法は、とても危険だと説いています。
何故なら、「壁掛けカレンダー」は持ち歩けないから。
このやり方の場合、出先では手帳を使うことになると思いますが、壁掛けカレンダーから出先で使う手帳へ、または手帳から壁掛けカレンダーへ書き写す一手間が発生することになります。
発達障害を持つ人がこれをやると、かなりの確率で書き忘れが発生します。
書き忘れがあるから、出先で予定が分からなくなったり、大事なアポをすっぽかしてしまったり…
こんなヤバイ事態にもなりかねません
この事態を対策するために、理想的な状態は何か?
それは、「手帳にメモした内容が、放っておいても勝手にカレンダーに転送されて表示される状態」だと著者は説きます
この状態を作り出すために、安価なタブレットを壁掛けカレンダー代わりにする方法が紹介されています
ライフハック:安価なタブレットを使って、壁掛けカレンダー代わりにする
【ポイント】
・中古の安いタブレットを購入
(googleカレンダーさえ動けばよいので、型落ちの安価なモデルでOK)
・デスクのカレンダーの位置に固定
・Googleカレンダーを表示し、予定が見えるようにする
・予定のメモや入力はスマートフォンから行う
・Googleアカウントでこの2つを同期させる
こうすると、「スケジュールをスマホから入力すると、家にかけてあるタブレット(カレンダー)に表示される状態」を作れるので、転記を忘れた…という事態を防ぐことが出来ます。
しかも、アラームやリマインド機能も使うことが出来ますので、やり忘れも減らすこともできるんです
「スケジュール管理は、家や会社の壁掛けカレンダー(卓上カレンダー)が便利なんだけど、手帳は出先で使うことが多いんだよな……」と思っている
手帳とカレンダー間の転記ミスで、手痛い失敗をしてしまったことがある
こんな悩みを一気に解決できる、便利なライフハックです
発達障害者が覚えておきたい標語
この本には発達障害者向けのライフハックが多数紹介されていますが、「休息」の取り方についても、色々と書いてあります。
その中で、ライフハックというほどではないけど、個人的にすごく心に刺さった標語を紹介したいと思います
「どんなときでも、休むのはベターな判断」
・休んでしまうことに罪悪感を覚えてしまう人
・休むことで、取り残されてしまう感覚に陥ってしまう人
いると思います。
その気持ち自体は、痛いほどよくわかる
でも、身体と心が悲鳴を上げているのに、「休むこと=悪いこと」という感覚があって休もうとはせず、そのまま無理をし続けて、結局は壊れてしまった人
僕は何人も見てきました。
「もう休みたい」と本心では思い始めた時点で、結構危ない状態なんです。
心と身体は、「頼むから休養してくれ」と言っているんですよ
なので、その声に素直に従い「一度休む」という選択肢をとるのは、ベストではないかもしれませんが、ベター(良い)な判断であることは間違いないと僕も思うんです。
なので、休養を取ることに罪悪感がある人は、是非この標語を思い出して、積極的に休むを取ることを考えてほしいです。
「休む」という判断を「よく頑張った」とほめてくれる人は、ほとんどいないでしょう。
「死ぬ気で頑張れ」という人はたくさんいるというのに、本当にひどい話だと思います。
しかし、あなたが「休む」と決めたその判断はいついかなるときであっても、ベターではあるのです、ベストではないにせよ。
誰もそれを間違いだとはいえないのです。
いついかなるときでも「休む」という判断は正しい。
そして、その苦しい判断をしたあなたは頑張っています。どうか、忘れないでください。
引用:発達障害サバイバルガイド
まとめ:発達障害サバイバルを読んだ感想
まとめ
・発達障害を持っているすべての人は、一度は読んでおいた方が良い、発達障害者にとっての聖書(バイブル)!
・参考になったところ
①机とイスはあなたの家の知的生産拠点
②発達障害的型付けの最重要アイテム「本質ボックス」
③すっぽかしをゼロにする「究極カレンダー」
・覚えておきたい標語
「どんなときでも、休むのはベターな判断」
発達障害を抱えて生きることになった僕が、参考にさせてもらった、支えになった本です
発達障害を持っていて、困りごとがたくさんある人
発達障害を持っている人が周りにいて、どう対策したらいいか分からない人
そんな人たちのヒントになるアイディアやライフハック、考え方が、たくさん詰まっているので、是非読んでみてくださいね。
「発達障害サバイバルガイド
出版社ダイヤモンド社