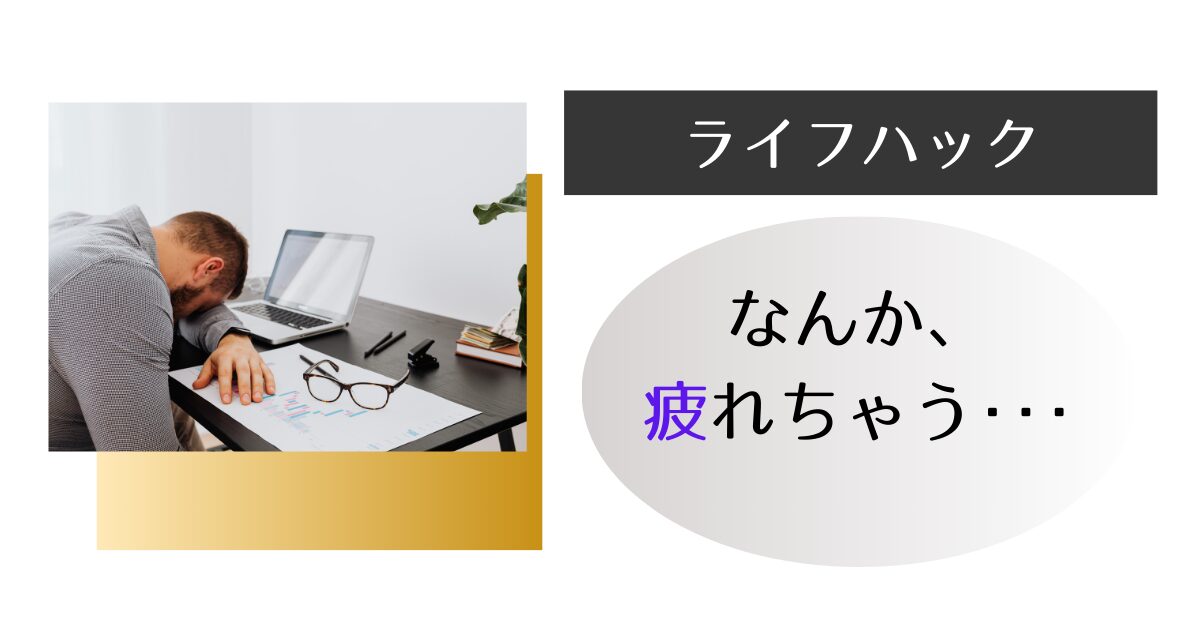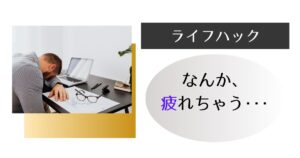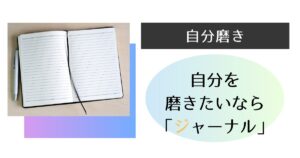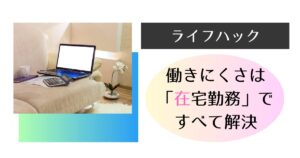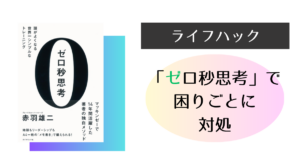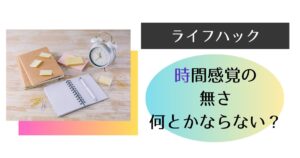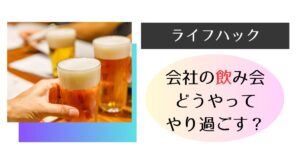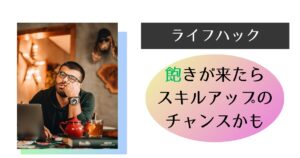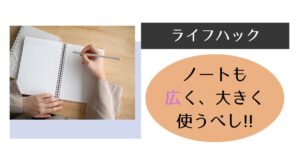- 「いつも疲れている気がする」
- 「他の人よりも仕事や生活で疲れやすい」
発達障害(ADHDやASD)を持つ人の多くが、いつも疲れている感覚を抱えています。
あらためまして こんにちは ゆーさくです
私自身も40歳を過ぎてADHD+ASDであることが発覚しましたが、振り返ると「なぜこんなに人より疲れてしまっているんだろう?」と感じ続けてきました。
 ゆーさく
ゆーさく
本記事では、発達障害の人が疲れやすい理由を脳科学・生物学の観点から解説し、日常でできる改善法をご紹介します。
・発達障害の人はなぜ疲れやすいのか?
・発達障害を持つ人 脳と栄養の関係
・発達障害を持つ人の疲れやすさ 対策案
発達障害の人はなぜ疲れやすいのか?
まず、なぜ発達障害を持つ人が疲れやすいのか? この部分から解説したいと思います。
①脳のエネルギー消費が大きい
発達障害の人は、脳の「前頭前野」を常にフル回転させています
これは、生産性が高い脳の使い方をしている・・・というわけではありません
ADHDの人
→「注意があちこちに移りやすい」ため、集中を維持するだけでも膨大なエネルギーを消耗
ASDの人
→「細かい情報処理を丁寧に行う」ため、他の人より処理に時間とエネルギーが必要
「あまり意味のないことに、オートで頭を使わされている」
こういったイメージを持っていただければと思います
要は、普通の人よりも脳のエネルギー消費が大きく、燃費の悪い状態であるということです。
②刺激に敏感で「疲れの種」が多い
発達障害を持つ人は「感覚過敏」が伴うことがあります。
発達障害の人は、「感覚が過敏」
- 騒がしい音
- 強い光
- 服やシャワーなどの水の触感
- 人の気配や視線
こうした刺激を人一倍キャッチしてしまうため、無意識のうちにエネルギーを消耗します。
例えば、オフィスの蛍光灯や空調の音でも、普通の人は気にしないのに、発達障害の人にとっては知らないうちに疲労してしまう原因になってしまいます
③「普通にふるまう」努力が疲労につながる
発達障害の人は、日常的に次のような努力をしています。
-
忘れ物やミスをしないよう必死に注意する
-
空気を読もうと頭をフル回転させる
-
自分の特性を隠して「普通」に見せようとする
発達障害を持つ人は「普通の人が難なくできることを、人よりも何倍も頑張ってようやくできている状態」
こういうことも多いです。
これらは外からは見えにくい負担ですが、積み重なることで「常に疲れている」状態につながります。
上記の内容が原因で、常に疲れやすく、緊張モード(交感神経)が常時発動して、心も体も満足に休まることがありません。
結果、疲れをとるための睡眠の質も悪くなり、
このように感じやすくなります。
発達障害を持つ人 脳の働きと栄養
また、発達障害の特性を持つ人の脳の働きと、栄養の関係性も無視はできません。
脳がスムーズに働くためには、エネルギーを生み出すための栄養素が欠かせません。
特に 鉄分・亜鉛・ビタミンB群 は、神経伝達物質の生成やエネルギー代謝に深く関わっています。
鉄分
「酸素を脳に届ける役割」を持ち、集中力や思考力を支える重要なミネラル。
→不足になると脳が酸欠状態のようになり、強い疲労感や集中困難を引き起こす。
亜鉛
ドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質の調整に必要で、気分の安定や意欲に関係。
→不足すると「やる気が出ない」「頭がぼんやりする」といった状態になる。
ビタミンB群
糖質や脂質からエネルギーを作り出す“潤滑油”のような存在
→不足すると、エネルギー代謝が滞り、慢性的な疲労感を感じやすくなる。
実際、一部の研究では 発達障害の人は、これらの栄養素が不足している傾向があることが示されています
すなわち、「疲れやすさ」や「集中力の低下」とも関わってくるということ。
そのため、脳の働きを助け、疲労感の軽減をはかるためにも、食事の工夫や必要に応じたサプリメントの利用が必要です。
もちろん「栄養だけですべて解決するわけではない」ですが・・・
体調のベースを整えることは、他の対処法の効果を高める土台にもなります。
発達障害を持つ人 疲れやすさの対策案
それでは、発達障害を持つ人が、少しでも疲れやすさを軽減できるようにするために、対策案を考えたいと思います
①刺激を減らす工夫をする
発達障害の特性を持つ人は、感覚が過敏であるがゆえに、通常の人よりも疲れやすいー
であれば、その刺激をできるだけ減らす方法を検討するのがいいと思います。
刺激を減らす工夫をしよう!
-
ノイズキャンセリングイヤホン
-
サングラスやブルーライトカット眼鏡
-
静かな作業環境の確保
僕の実感でいうと、この刺激を減らす工夫をすることは、即効性が高く、効果も高いと感じました。
僕は、音による刺激に敏感で、周りに人や物音がする環境に居続けると、みるみる疲れてしまう特性があります。
なので、イヤフォンや耳栓を活用したり、可能な時は在宅で仕事をさせてもらうことにしています。
体力や精神力がかなり温存できるので、パフォーマンスも上がりました。
②脳の負担を減らすツールを使う
発達障害の特性を持つ人は、常に色々なことを考えていて、頭のリソースをムダに消費している傾向があります
また、発達障害の特性を持つ人は、ワーキングメモリが弱いという弱点を持つ人が多いです
なので、頭のリソースを消費しない工夫が必要です。
頭のリソースのムダ使いを減らす工夫
- スマートタグ(忘れ物、探し物防止)
-
バレットジャーナル(頭の中を整理する)
-
メモアプリ・タスク管理アプリ
探し物をしている時間や、常に何かを考えて覚えておくことは、脳のワーキングメモリを大量消費します。
覚えなくてもいい状況を、意図的に作り出すことで脳の余力を確保することができます。
③栄養を意識する
発達障害の特性を持つ人は、アドレナリンやドーパミンといった脳内分泌が健全に働いていない状態になりがちです。
これは、発達障害を持つ人は通常の人に比べ、体内の代謝反応が働いていないから・・・という説があるそうです
▼参考記事▼


代謝反応を正常に働かせるためには、たんぱく質やビタミンやミネラルといった栄養素を、意識的に摂取していく必要があります。
でも、現代社会の食生活では、これらを食事から十分とることは、正直難しいと思います
補助的に、プロテインやサプリを活用しましょう。
比較的、即効性が高かったもの&効果が実感できたものを中心に、対策案をご紹介させていただきました。
疲れやすい状態が慢性的に続いてしまうなんて・・・
ハッキリ言って、人生大損しているといっても大げさではありません。
疲労が残ってしまうと、何にも楽しいことができなくなるのと一緒ですから。
工夫次第でこの疲労度は軽減できるので、実施しやすい方法を試してみてくださいね。
まとめ 発達障害の人が「疲れやすい理由と対策法
まとめ
・発達障害の人はなぜ疲れやすいか
①脳のエネルギー消費が激しい
②刺激に敏感で「疲れの種」が多い
③「普通にふるまう」努力が疲労につながる
・発達障害をもつ人脳の働きと栄養の関係性
鉄分・亜鉛・ビタミンB群 は、神経伝達物質の生成やエネルギー代謝に深く関与している
→発達障害の人は、これらの栄養素が不足していて、「疲れやすさ」や「集中力の低下」の傾向がある
・発達障害を持つ人が疲れないようにする対策法
①刺激を減らす工夫をする
②脳の負担を減らすツールを使う
③栄養を意識する
発達障害の特性を持つ人は、知らず知らずのうちに脳のリソースをゴリゴリと削り取られています
「疲れやすい」のは、脳の特性や体質的に考えて、無理もないことです。
ただ、「いつも疲れてしまうけど、そういう特性だから仕方ないのかな」と悩んであきらめかけている人も、工夫次第で驚くほど生活が楽になります。
まずは、できることから一つずつ試してみてください。
~おわり~
▼ご意見はこちらまで▼