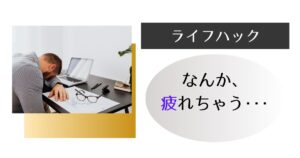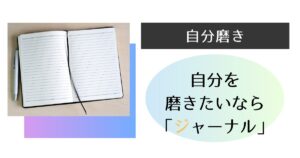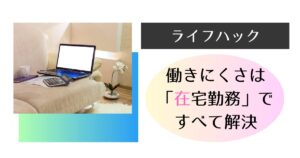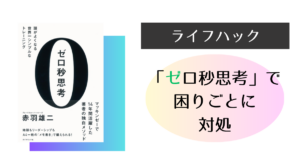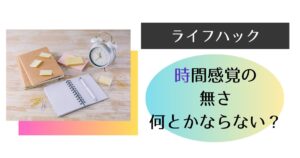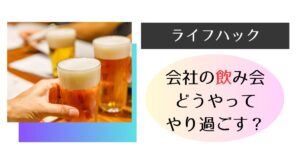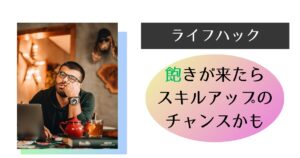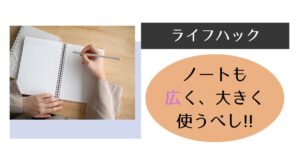みなさん こんにちは ゆーさくです
僕は40歳を過ぎてから、自分がADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の特性を併せ持つ、発達障害グレーゾーンであることを知りました。
特に悩んでいたのが、仕事をしていない夜や休日でも、頭の中がずっと忙しく動き続けてしまうことです。
その原因は、脳の偏桃体(へんとうたい)の暴走によるものでした。
今回紹介するのは、この脳の偏桃体(へんとうたい)暴走を抑えるため、日常に瞑想を取り入れてみた話です
発達障害と偏桃体の暴走の関係
発達障害を持つ人は、脳の偏桃体という部分が過剰に働きやすい傾向があると言われています。
偏桃体は感情や不安を司る部分で、これが暴走すると以下のような状態になります。
- 不安が強くなる
- ネガティブなことを繰り返し考えてしまう(反芻思考)
- 眠れなくなる
僕にも、身に覚えがあります。
夜、布団に入ってもなかなか寝つけず、やっと眠れても変な時間に目が覚めてしまい、そのまま朝まで眠れない──そんな日々が続きました。
仕事のこと、人間関係のこと、ちょっとしたミスや過去の失敗……。
思い出したくもないのに、頭の中で延々と再生されてしまう。
止めたくても止まらない。
 ゆーさく
ゆーさく
脳が過剰暴走し、不安に苛まれる──そんな状態が続くと、満足に眠ることが出来ず、心も体もどんどん疲弊していきます。
結果的に、心療内科にお世話になることになりました。
幸いにも睡眠導入剤で眠れるようにしてもらい、大事には至りませんでした。
ただ、不安にさいなまれて眠れなくなり、その度に睡眠導入剤に頼り強引に眠れるようにする・・・
これって、なんか根本的に間違っているような気がしました。
今後も、こんなことを繰り返していれば、いずれはうつのような深刻な事態になってしまうでしょう。
脳(偏桃体)の過剰暴走を、なんとかコントロールして抑え込む方法が必要があります。
そこで、僕が試してみたのが、瞑想(マインドフルネス)でした。
瞑想(マインドフルネス)で、脳(偏桃体)の過剰暴走を抑え込む
瞑想(マインドフルネス)とは?
瞑想(マインドフルネス)とは、意識的に「今この瞬間」に集中することで、雑念を減らし、心を落ち着けるための手法です。
仏教由来の伝統的な瞑想法をベースに、近年では科学的な研究も進み、ストレス軽減や集中力向上などの効果が実証されています。
名高る有名企業も、瞑想を取り入れているところがあるくらいです。
発達障害を持つ人は、過去の失敗や未来の不安を特に考えすぎてしまう傾向があります。
思い出したくもないのに、勝手に不安やイヤなことが浮かび、気が付いたらオートメーション(自動)で考えてしまい、気が付いたら心身に不調が表れてしまう…
ホント、タチが悪いから改善する必要があります。
そのため、瞑想を通じて「今ここ」に意識を向ける練習をすることで、脳の偏桃体の暴走をコントロールし、心の安定を得られる効果が期待できるのです。
瞑想(マインドフルネス)は今更だけど、めちゃくちゃ効果がある
最近は「マインドフルネス」という言葉もすっかり広まり、多くの人がその概念くらいは知っていると思います。
ただ、正直なところ、
「瞑想って本当に効果あるの?」
「スピリチュアル的な感じがして、なんか怪しい・・・」
こう疑問に思っている人は少なくないはずです。
僕も最初は半信半疑でした。
でも実際にやってみると、自分が思っていた以上に効果があったんです。



瞑想は、脳の過剰な暴走を抑え、今この瞬間に意識を向ける、れっきとした科学的に証明されている『技術』です。
発達障害の特性があると、つい過去の失敗を思い出したり、未来の不安を考えすぎたりしてしまいます。
でも、瞑想をすることで、「今ここ」に集中する習慣が身についてきます。
- 不安感が軽減される
- 反芻思考(ネガティブなことを繰り返し考える)が減る
- 頭の中がスッキリして、物事に集中しやすくなる
瞑想(マインドフルネス)を習慣化した結果、こういった効果を感じられるようになりました。
オーソドックスな瞑想のやり方
瞑想の基本的なやり方はシンプルです。
基本的な瞑想のやり方
- 静かな場所に座る(椅子でも床でもOK)
- 目を閉じて、呼吸に意識を向ける
- ゆっくり深呼吸をする(鼻から吸って、口から吐く)
- 雑念が浮かんでも気にせず、「あ、考えてるな」と気づいて呼吸に戻る
最初は5分程度から始めるのがおすすめです。
慣れないと、雑念がどうしても浮かんできてしまうと思いますが、最初はそれでOKです
雑念が浮かんでも、すぐに「呼吸」に意識を向けることに集中しましょう。
生活の中でできる「ながら瞑想」
オーソドックスな瞑想が出来るならば、それが一番いいのですが・・・
中々それが難しい時もあると思います。
座って目を閉じる・・・という行為が少々面倒で敷居が高かったり、会社のオフィスだと人の目が気になって、出来なかったりします。



実は、瞑想は生活の中の何気ない動作をやりながらでも、行うことができます。
いわゆる「ながら瞑想」です。
ここでは、比較的取組みやすい「ながら瞑想」を紹介します
1. 寝ながら瞑想
夜、眠る前だったり、夜中目が覚めて寝付けない時だったり、ベットや布団に横になって寝ながらでも、実は瞑想はできます
寝ながら瞑想のやり方
- 仰向けになり、体の力を抜く
- 呼吸に意識を向け、ゆっくり深呼吸する
- 身体の感覚に意識を向け、足→ふくらはぎ→太もも……と、順番にリラックスさせる
わざわざ座って、瞑想をするぞ!と意気込まなくても、横になっている状態でも出来るので、横になってゴロゴロしているときのついでにやってみてはいかがでしょうか?



2. 歩きながら瞑想
通勤やウォーキングの習慣がある人におススメなのが、「歩きながら瞑想」です
歩行する時間も、実は瞑想の時間にすることが出来るんです
歩きながら瞑想のやり方
- 歩くときに、足の裏が地面に触れる感覚を意識する
- 右足、左足、と順番に「今ここ」に集中する
- 呼吸に意識を向けながら、ゆっくり歩く
歩いたときの、足の裏の感覚、足の動き、呼吸に意識を集中すると、自分が思った以上に色々な情報が感じ取れるはずです。
そこを意識することで、「今ここ」に集中している状態になることが出来ます。
3. 食べながら瞑想
それから、普段食事をするときにも、「瞑想」を取り入れることが出来ます
食べながら瞑想のやり方
- 一口ずつ、ゆっくりと噛む
- 食材の味や食感をしっかり感じる
- 口の中でどんな変化が起きているか意識する
物を口に入れて食べる時、しっかり集中して意識してみると、実に色々な感覚が感じ取れることと思います。
その感覚をしっかり感じ、味わうことでも「今ここ」に集中した状態=すなわち瞑想(マインドフルネス)状態になることが出来ます
大事なのは、「今ここ」に集中する感覚をつかむことです。
通勤で歩いたり、食事をしたり、寝るために横になったり…
生活をするなかで、何気なくやっているこれらの動作に、「瞑想」を取り入れれば、人の目を気にすることなく気軽に始められます。
そして、無理なく「今ここ」に集中することを習慣に出来るはずです。
こういう日常生活の中に「瞑想」を取り入れる、「ながら瞑想」から始めてみてはいかがでしょうか?



瞑想(マインドフルネス)に役立つ書籍、アプリ紹介
瞑想(マインドフルネス)をもっと詳しく知りたい、みっちり取り組みたいという人に向け、役立つ書籍やアプリを紹介します
①マインドフルネス瞑想入門
瞑想(マインドフルネス)のやり方の基礎を知りたい方に、おススメの書籍です
音声ガイドをダウンロードして、いつでも瞑想(マインドフルネス)に取組めます。


②頭を「からっぽ」にするレッスン
あの有名なYouTuber「サラタメ」さんが絶賛している、マインドフルネスに生きるための瞑想のやり方を紹介した書籍です


③Awarefy(アウェアファイ)
マインドフルネスのやり方や記録はもちろん、メンタルの状態を可視化したり、認知行動療法の観点からのアドバイスを受けられたり・・・
頼れるメンタルパートナーになってくれるアプリです
引用:Awarefy
まとめ
まとめ
- 発達障害の人は偏桃体が暴走しやすく、不安や反芻思考に悩まされる
- 瞑想(マインドフルネス)は「今ここ」に意識を向ける技術
→偏桃体の暴走を抑え、不安を軽減できる
- オーソドックスな瞑想だけでなく、日常生活の中でも取り入れられる「ながら瞑想」もおススメ
- 瞑想を続けることで、心が軽くなり、生きやすくなる
僕は瞑想を取り入れることで、不安感が減り、気持ちがスッキリするようになりました。
発達障害の特性がある人ほど、この効果を実感しやすいかもしれません。
特別な道具もいらず、すぐに始められるので、ぜひ一度試してみてくださいね。
~おわり~
↓ご意見はこちらまで↓